FXや仮想通貨の売買や株式投資をしている方から「投資活動で出た損益は、ふるさと納税の控除限度額に影響はあるのか?」「控除申請が複雑になったりしないか?」という質問を頂くことが増えてきました。
この記事では、具体的な計算方法や源泉徴収される特定口座保有の有無なども踏まえた注意点を税理士が詳しく解説します。
あわせて確定申告の方法についてもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
本記事は、加藤公認会計士・税理士事務所の監修のもと作成しております。
- 損失が出た場合は控除限度額に影響なし
- 利益が出た場合は控除限度額が増える

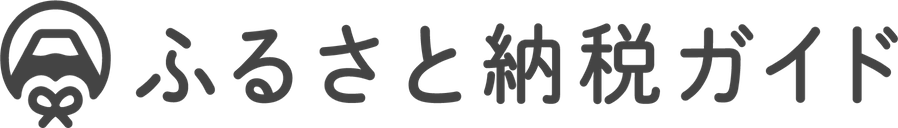



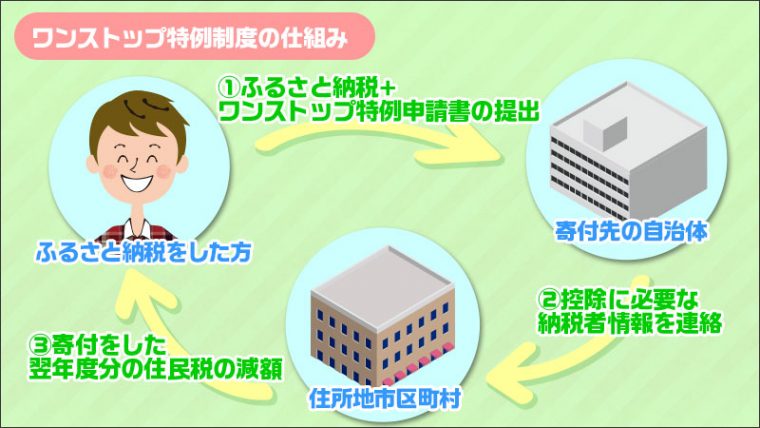

 また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。
また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。 上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。
上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。


