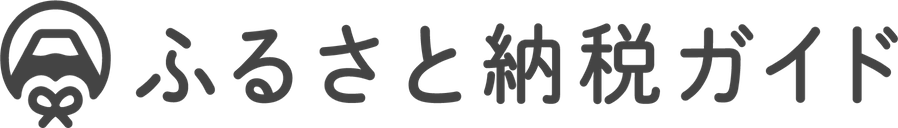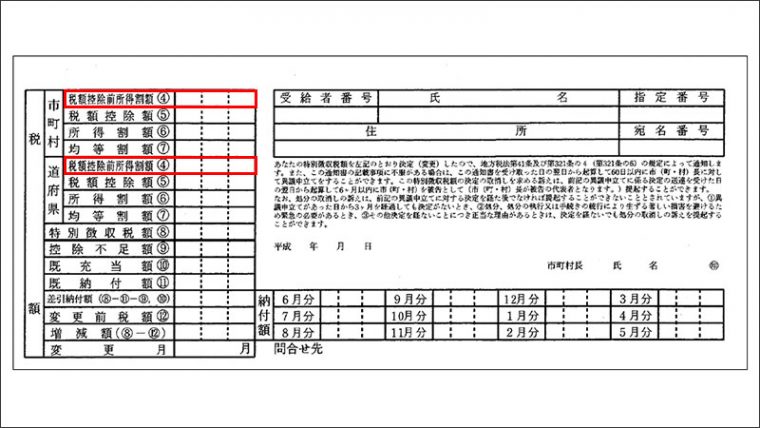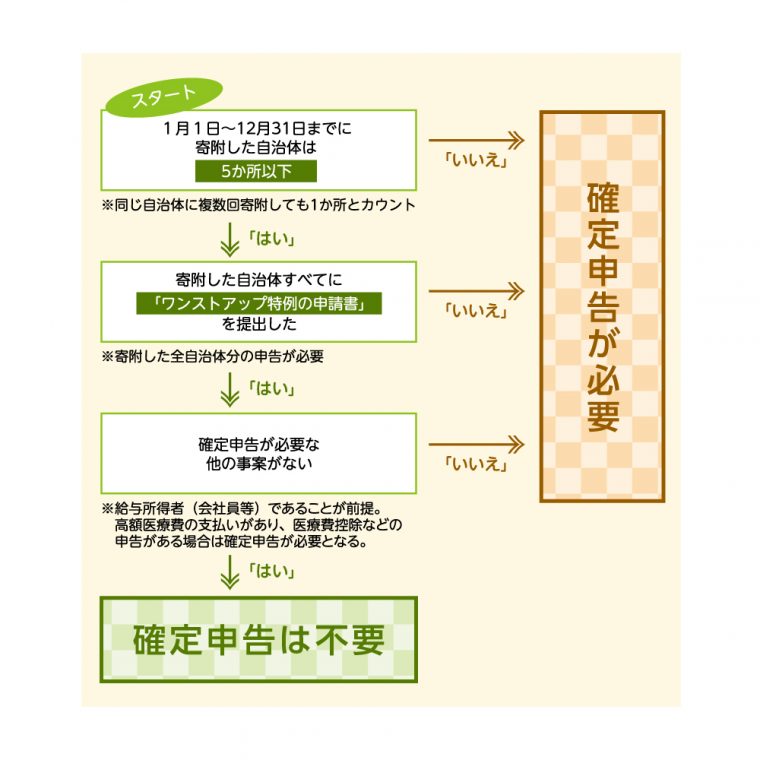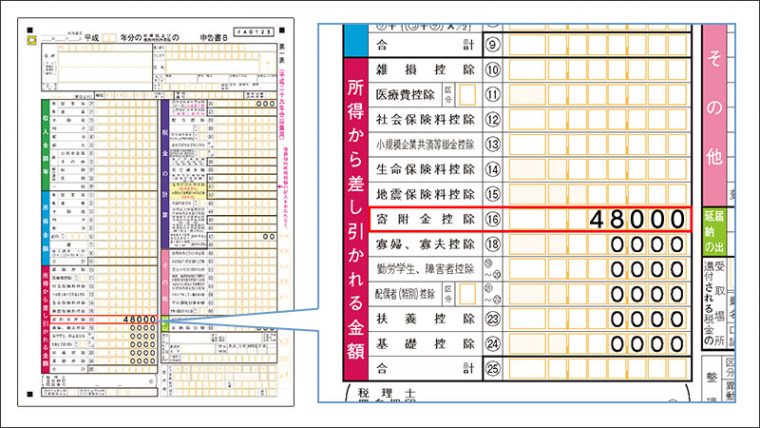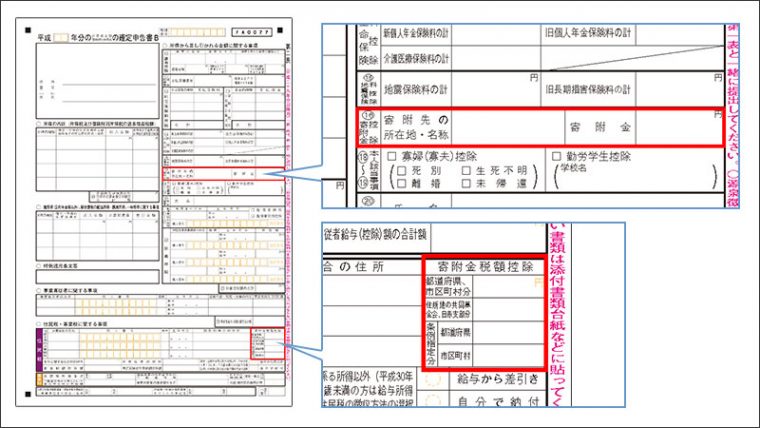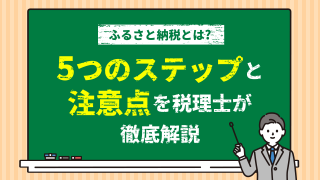地域の特産品やなどの返礼品がもらえることで話題のふるさと納税ですが、個人事業主やフリーランスの方、そして年金受給者の方も活用できます。
この記事では自営業の方や年金受給者の方がふるさと納税を利用する方法と、税控除の限度額などの注意点を税理士が詳しく解説します。
※本記事は、加藤公認会計士・税理士事務所の監修のもと作成しております。
個人事業主の方や年金受給者の方向けのシミュレーションもご用意していますので、手っ取り早く限度額の目安が知りたい方は最短2クリックのかんたんシミュレーションをご活用ください。